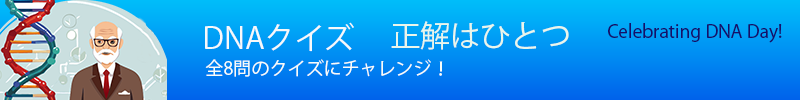News
ニュース
2025.4.21
FeaturesTOPICSニュース
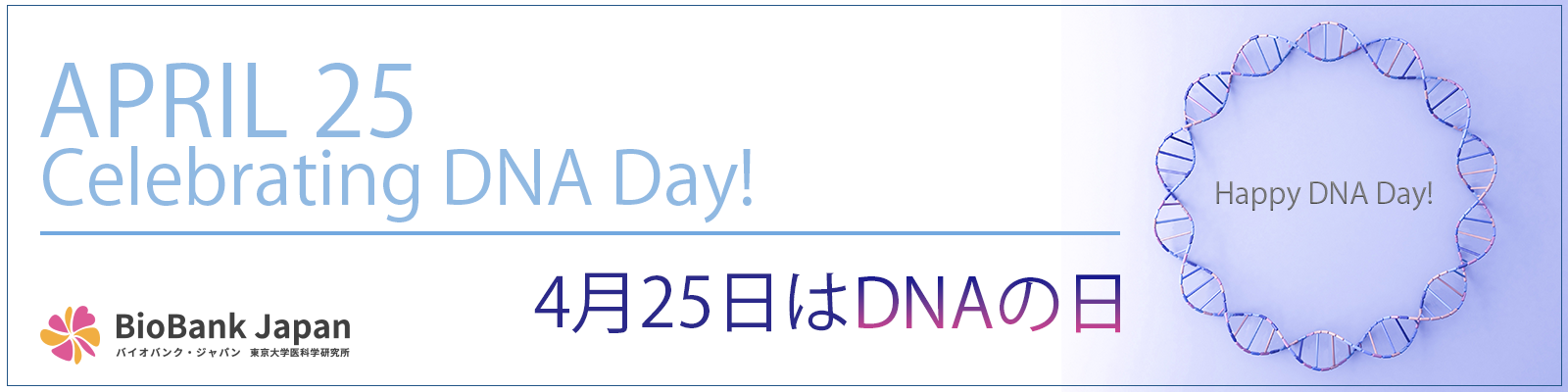
4月25日はDNAの日です。1953年のこの日、DNA(デオキシリボ核酸)が二重らせん構造をしていることが発表されました。またちょうど50年後となった2003年の同日には「ヒトゲノム計画」の完了が宣言されています。70年前の歴史的な発見とその後の偉業を経て、DNAおよびDNAに含まれる遺伝情報全体を表す「ゲノム」の研究は、私たち自身を知り、健康な生活を支える基盤となっています。
ゲノム科学は飛躍的な進歩を遂げました。ヒトゲノム計画の終了から数年後に登場した次世代シーケンサー[1]のおかげで、大規模なゲノム解析が従来に比べてはるかに低コストで、かつ高速に行えるようになりました。また、たくさんの方々からのデータを解析するゲノムワイド関連解析(GWAS)[2]により、さまざまな疾患や形質にかかわる遺伝的要因が次々と明らかになっています。こうした知識は、ひとりひとりの体質に合った「個別化医療」の実現を推し進めています。
例えば診断名は同じ大腸がんであったとしても、その原因となった遺伝子の変化は人それぞれです。その人の遺伝子の変化に狙いを定めた治療法は、従来の一律的な治療に比べて効果が高く、副作用も少ないことが期待されています。さらに、近年では、遺伝子からタンパク質が作られるプロセスがどのように調節されているかの仕組みもわかりつつあります。近年では、AIを活用した解析や、遺伝子の配列を狙いを定めて改変するゲノム編集技術の発展も目覚ましいものがあります。これらの技術は基礎研究を加速させ、病気にいたるメカニズムの理解をさらに深めています。こうした研究から得られる知見は、より効果の高い、個々の人の病気や体質にあった個別化医療の開発に役立つと期待されています。
今後もゲノム科学のさらなる発展により、さまざまな疾患に対する革新的な治療法が生まれることでしょう。DNAの日を迎えるにあたり、私たちはこれまでの進歩を振り返るとともに、未来への期待を新たにします。
1953年4月25日に、ジェームズ・ワトソンとフランシス・クリックらによるDNAの二重らせん構造に関する論文が国際科学誌Natureに掲載され、科学界に衝撃が走りました。そしてこの発見から半世紀を過ぎた2003年の同日には、1990年に始まり、日本も参加した「ヒトゲノム計画 」が事実上、完了したという宣言がされました。約30億対の塩基配列からなるヒトの設計図とでも言うべき全ゲノム情報の解読を目指したこのプロジェクトは、生命科学の分野では初めての国家間レベルの国際協力計画で、その成果は人類の共通財産として公開されています。
このように、4月25日はゲノム科学にとって重要な意味がある日です。当初は、「ヒトゲノム計画 」を主導した国の1つである米国が、その年に限って2003年4月25日を「全米DNAデー」と定めたのですが、その後、この記念日に賛同する世界の学術・研究機関などが毎年のように祝うようになり、この日は世界的な記念日として認知されるようになりました。
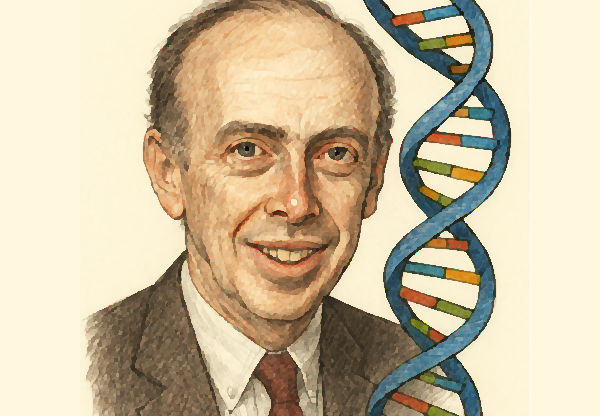
「DNAの日」は、ゲノム研究に携わる学術界や産業界だけでなく、広く市民がこの日の意義に思いをはせ、科学技術の進歩がもたらす未来について考える日です。ゲノムやDNAに関する理解を深め、社会への影響や倫理面を含めた課題について話す機会でもあります。遺伝情報に関する不当な差別やプライバシーの侵害を無くすこと、そして遺伝情報の責任ある利用に関する議論は、ゲノム研究の成果を社会に役立て、より良い未来を切り開く上で極めて重要です。
バイオバンク・ジャパン(BBJ)は、全国12の協力医療機関を受診された患者さんからご提供いただいた血清・DNAなどの生体試料と医療情報を保管し、それらをゲノム医療の実現を目指す研究に提供する疾患バイオバンクとして、「DNAの日」の理念に深く賛同します。BBJはひとりひとりの体質に基づいた、より効果的で適切な「個別化医療」や「個別化予防」の実現に向けて貢献していきます。
[1]次世代シーケンサー 超高速シーケンサーとも呼ばれる。従来のDNA配列決定に用いられていたサンガー法とは原理的に異なる方法で、大量のDNAの塩基配列を解読することができる装置である。1台の装置で一度に5億から1000億塩基の解読を行なうことができる。
[2]ゲノムワイド関連解析(GWAS) ゲノムの全領域に散在するDNAレベルの個人差(変異・多型・バリアントなどと呼ぶ)と疾患発症リスクなどといった形質との因果関連を網羅的に検討する遺伝統計解析手法。多くのGWAS研究では、DNAレベルの個人差の中でも一塩基多型(SNP)を対象にしている。単一遺伝子による希少な遺伝性疾患ではなく、高血圧や糖尿病といった多くの遺伝因子(と環境因子)がかかわる疾患の解析に用いられる。