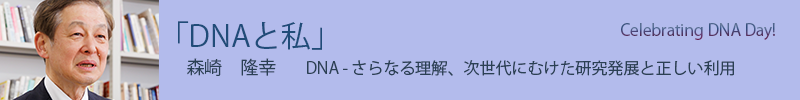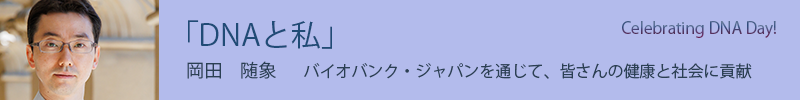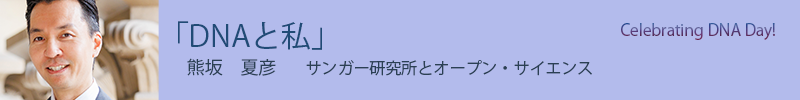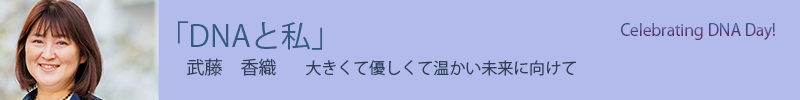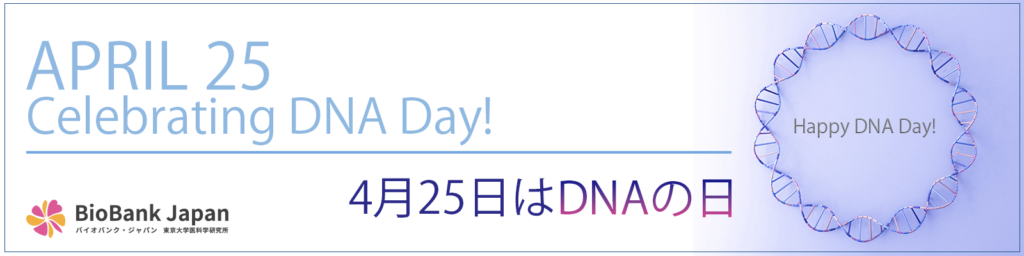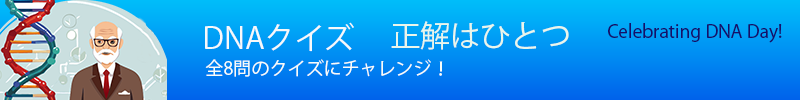News
ニュース
2025.4.23
FeaturesTOPICSコラム
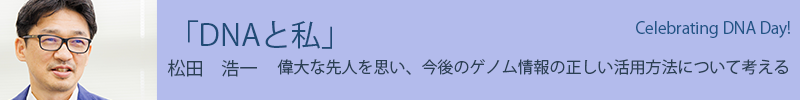
私が研究生活をスタートさせたのは、ゲノム研究が大きな転換を迎える直前の1999年4月になります。当時は一つの遺伝子のDNA配列を決定するだけでも大変な作業という時代でしたが、翌2000年6月には、ヒトゲノムの塩基配列のワーキングドラフトという膨大な研究成果が発表されました。フランシス・コリンズ博士(「ヒトゲノム計画」代表)、クリントン米大統領、ブレア英首相らがホワイトハウスから会見する映像がとても印象に残っています。そして2003年にはヒトゲノムの解読完了が宣言されました。
当時、大学院生だった私が所属していた研究室では、研究室のメンバーが旧式のシークエンサーを使って一塩基多型(SNP)というバリアントのカタログを作成していたことを覚えています。その後は、ゲノム研究が飛躍的に進歩し、新しい研究手法がどんどん出てくるいわゆるポストゲノムといわれる時代に突入しました。私自身、ゲノム研究の黎明期に研究者となったことが、DNAやゲノムの研究に深く携わるようになったきっかけになっていますし、時代の変化を肌身に感じた26年でした。
バイオバンク・ジャパン(BBJ)は、「ヒトゲノム計画」が完了した2003年に設立されました。2003年といえば、日本では個人情報保護法が制定され、個人情報の最たるゲノムデータの研究利用に対する風当たりや批判的な風潮がありました。そんな中で、オーダーメイド医療実現を掲げ、適切な同意のもとで生体試料(血清・DNA)を収集し、研究に利用するという仕組みを立ち上げた中村祐輔先生(当時 東京大学医科学研究所 教授、現 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長)は、卓越した先見の明をお持ちだったと思います。BBJは立ち上げから22年たった今でも世界に誇る研究のインフラとして活用され続けています。また中村先生自身が世界に先駆けて2002年に実施したゲノムワイド関連解析(GWAS)は、今ではゲノム研究のスタンダードな手法となり、世界中で6000以上のGWASを使った論文が報告され、非常に多くの新しい発見をもたらしています。
BBJは患者さんから提供いただいた貴重な生体試料や情報をお預かりする疾患バイオバンクとして、病気のメカニズムを明らかにするだけではなく、基礎研究の成果を医療に役立てることを大きな使命としています。多くの研究成果に基づき、今後ゲノム情報が医療現場などで活用される場が拡大すると見込まれます。一方でゲノム情報に対する知識や理解の不足から、不当な差別やプライバシー侵害などの人権問題が発生するおそれもあり、我々基礎研究者は、ゲノム情報の正しい活用方法についても情報発信していく必要があると感じています。「DNAの日」にあたり、偉大な先人たちの研究成果を思い返すとともに、今後、我々がその上にどうプラスアルファの成果を積み上げてゲノム医学の進歩や人々の健康に貢献ができるのかといったことを改めて考えたいと思います。
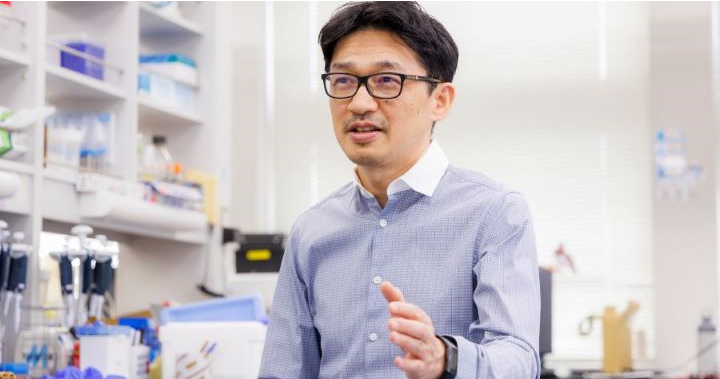
東京大学医科学研究所 ヒトゲノム解析センター 特任教授 / バイオバンク・ジャパン 代表
東京大学大学院新領域創成科学研究科 メディカル情報生命専攻 教授
1994年3月東京大学医学部医学科卒業。1994年6月東京大学医学部付属病院整形外科入局。2003年1月米国ベイラー医科大学 博士研究員。2003年3月東京大学大学院医学系研究科修了 博士(医学)取得。2009年11月東京大学医科学研究所 ヒトゲノム解析センター 准教授。2015年東京大学大学院新領域創成科学研究科 クリニカルシークエンス分野 教授。2022年東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター 特任教授